「クリスマスとサンタクロースってどんな関係があるの?」
とお考えではありませんか?
僕も子供のころから、クリスマスといえばサンタクロース、サンタクロースといえば煙突から入って靴下にプレゼントを入れてくれる人、つまり純粋に、「なんていい人なんだ…。」と考えていました。笑
でも大人になってよく考えてみると、クリスマスとサンタクロースの関係性もほとんど知らなければ、なぜ煙突や靴下が出てくるのかなど、正直知らないことばかりだったんです。
そんな僕も小学生の子を持つ親となりまして、クリスマスやサンタクロースのことについて子供たちに話する機会も増えたこともあり、気になっていたところは色々と調べつつ、今ではこれらのことをしっかり説明できるようになりました。
ということで今回は、クリスマスとサンタクロースの関係性や、なぜ煙突や靴下というものが登場するのかなど、クリスマスの気になるところについて書いていますので、一緒に見ていきましょう!
スポンサーリンク
クリスマスとサンタクロースの関係は?

クリスマスとサンタクロースは、【もともと別のお話が合わさったもの】です。
まずそもそもクリスマスとは、キリストの降誕祭(こうたんさい)を意味します。
よく12月25日は「キリストの誕生日」と解釈されることがありますが、実際にはキリストの誕生日というのは諸説があって特定がされておらず、あくまで「降誕を記念する日」、つまりイエス・キリストがこの世に舞い降りたことをお祝いするお祭りがクリスマスというわけです。
キリストが生まれた日ではなく、人々の前にお目見えされた日というような解釈ですね。しかし実際に降誕したのも12月25日であるとは限らず、他にも5月20日であるなどの説もあります。
12月25日が降誕祭という記念日になったのは、遥か昔4世紀ごろ、すでにこの時期に古代ローマ帝国内で催されていた「冬至のお祭」が起源になったと考えられています。
サンタクロースのモデルとなった聖ニコラオス
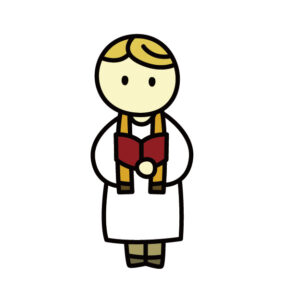
ここでサンタクロースのモデルとなったと考えられている、聖ニコラオスというキリスト教の聖人のお話が出てきます。
ニコラオスはローマ帝国リュキア属州のパタラという町に生まれ、のちに古代都市ミラでキリスト教の大主教となった、3世紀から4世紀(270年~345年ごろ)に実在したとされる人物です。
ニコラオスがキリスト教の司祭を務めていたころ、かつては豪商であったが当時貧しい暮らしをしていた娘のいる家庭に、3度に渡り金貨を投げ入れ、その家庭を救ったという逸話が残されています。
その際に金貨を家の窓あるいは煙突から投げ入れ、それがたまたま部屋に干してあった靴下の中に入ったとも言われており、この話が今でもサンタクロースにまつわる煙突や靴下というシチュエーションのもとになっているんですね。
そこから時代を経て、クリスマスにはサンタクロースが子供たちにプレゼントを配るという風習に変わっていきました。
ちなみにサンタクロースの名前は、聖ニコラオス(セント・ニコラオスまたはサント・ニコラオス)がなまり、このように呼ばれるようになったといいます。
サンタクロースの煙突や靴下のイメージには、ちゃんとこれにまつわる人物の伝説があったんですね。
ということでクリスマスとサンタクロースの関係は、同じくキリスト教のお話という接点がありますが、別のお話が時代を経て今のような関係になったというわけです。
僕も最近まで、サンタクロースは神様の知り合い?キリストの親戚?というようなイメージがありましたが、これで関係がよくわかりすっきりしました。(^^)
スポンサーリンク
トナカイや赤い服はどこから来たの?

クリスマスやサンタクロースの由来について見てきましたが、他にも「サンタクロースといえばこれ」というものがありますよね。
サンタを乗せたそりを引くトナカイであったり、サンタの赤い衣装であったりと気になるところがありますので、あわせて見ておきましょう。
トナカイは絵本の設定から?
古代より伝えられてきたクリスマスの風習ですが、1800年代になり絵本が出版されるようになると、サンタクロースのお話がたびたび描かれるようになっていきました。
その中に、「トナカイの引くそりに乗ったサンタクロース」や、「ふくよかな体系の老人の姿のサンタ」、「寒い国からやってくるサンタ」など、今のサンタクロースのイメージとなる絵が登場し、これらが総合的に今のサンタクロース像を作り上げてきたようですね。
ちなみにそりを引くトナカイは最大で9頭。先頭を走る赤い鼻のトナカイの名前はルドルフという名前が付けられています。
なぜトナカイなのかですが、寒い地方に生息していて立派な角や体格のあるトナカイが、当時の絵本の作者のイメージにぴったりだったようですね。
ちなみにサンタクロースの赤い服は、コカ・コーラ社の広告がきっかけで定着したという説もありますが、それ以前にモデルとなったキリスト教の司祭服のマントの赤色から来ているなど、諸説あります。
でも国によっては青い服のサンタや、緑の服のサンタなどもいて様々なようですよ。
世界中で親しまれているクリスマス。
長い歴史や多様な文化の中で、今のスタイルが作られてきたということなんですね。
おわりに
あらためてクリスマスとサンタクロースの関係について見てきましたが、歴史や伝説があるなかなか奥深い話だったんですね。
しかし確かに僕も子供のころにあまり詳しく聞いてもおそらく理解できなかったでしょうから、いろんな絵本や物語を見ては想像を膨らませていました。
今思えばどれも夢のある話でしたねぇ。
多くの国で子供たちに受け継がれている話と思うと、なんともロマンを感じます。
クリスマスやサンタクロースの由来を知って、さらにクリスマスを楽しみましょう!(^^)
他にもクリスマスに関する記事があります。
それでは今回はこの辺りで。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
スポンサーリンク



コメント